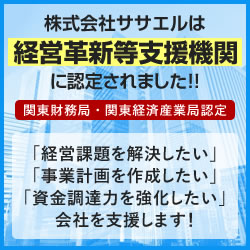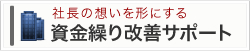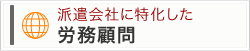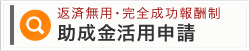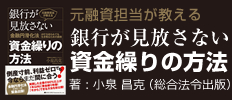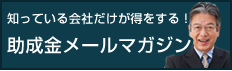- 株式会社ササエル ホーム
- 派遣ニュース
【派遣法を読み解く】第11条 変更の届出 [2020.12.08]
第11条は、
氏名や住所等に変更があったときは、遅滞なく届け出をすること。
事業所の新設に係るものであるときは、その事業所の事業計画書その他必要書類を添付する必要があること。
厚生労働大臣は、新設された事業所の数に応じた許可証を交付すること。
派遣元事業主は、変更の届出により許可証の記載事項が変更される場合は、書換えを受けなければならないこと。
等が記載されています。
【派遣法を読み解く】第10条 許可の有効期間等 [2020.12.04]
許可の有効期間は、許可の日から起算して3年です。
更新を1度受けた場合は、
有効期間満了する日の翌日から5年となります。
【派遣法を読み解く】第9条 許可の条件 [2020.12.03]
労働者派遣の許可を行うときに、条件を付したり、変更することができるとされています。
ただし、条件を付す場合は、
当該許可に係る事項を確実に実施させるために必要最小限度なものに限られ、
かつ、
不当な義務を課してはならない、
とされています。
【派遣法を読み解く】第8条 許可証 [2020.12.02]
厚生労働大臣は、労働者派遣を許可したときは、その事業所のの数に応じて、許可証を交付します。
一般的に許可申請書が受理された月の3か月後の初日に許可されます。
この許可証は事業所に備え付けておく必要があります。
エントランス近辺に掲示している会社が多いと思います。
許可証を亡失、滅失したときは、速やかに再発行を受けることも規定されています。
【派遣法を読み解く】第7条 許可の基準等 [2020.12.01]
労働者派遣の許可を受けるためには、
様々な書類を提出する必要があります。
1号では「専ら派遣」を禁止しています。
「専ら派遣」とは、派遣先を特定の1社または複数の会社に限定すること、です。
(ただし、10分の3以上が60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇入れた者)の場合を除きます。
2号では「キャリア形成支援制度」を有すること、派遣労働者の「雇用管理体制」が整備されていること
キャリア形成支援制度とは、キャリアに見合った教育訓練計画を作成・実施する制度のことです。
3号では、派遣労働者の「個人情報の管理体制」ができていること
労働者派遣の許可を得るには、実地確認が行われる理由の1つは、
個人情報管理体制ができているかの確認です。
4号はその他、労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること
基本は書面内容を確認して判断されることになります。
また、厚生労働大臣が許可しないと判断したときは、遅滞なく、理由を示して通知するとされています。
【派遣法を読み解く】第6条 許可の欠格事由 [2020.11.30]
ここでは労働者派遣事業を行えない者を定めています。
一部を抜粋して記載しますが、
禁固以上の刑や
労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定であって政令に定めるもの等による罰金の刑 等
・・・執行が終わり、又は受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない
労働者派遣事業の許可を取り消された者
労働者派遣事業を取り消された法人の役員
・・・当該取消の日から起算して5年を経過しない
など、
労働者派遣事業の欠格事由が定められています。
【派遣法を読み解く】第5条 労働者派遣事業の許可 [2020.11.20]
第5条では、労働者派遣事業の許可を受けるには、
どういった書類を提出すればよいかについて、
大枠で記載されています。
・申請書
・事業計画書(労働者派遣事業を行う事業所ごと)
・その他厚生労働省令で定める書類
最後に、
厚生労働大臣が許可をしようとするときは、
あらかじめ労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
と定めていますので、
申請書等が労働政策審議会を通れば、
ほぼ許可を得ることができることになります。
【派遣法を読み解く】第4条 業務の範囲③ [2020.11.13]
派遣法には定められていませんが、
以下の業務については、
労働者派遣事業を行うことは禁止されています。
・弁護士
・外国法事務弁護士
・司法書士
・土地家屋調査士
・公認会計士
・税理士
・弁理士
・社会保険労務士
・行政書士
・建築事務所の管理建築士
【派遣法を読み解く】第4条 業務の範囲② [2020.11.11]
労働者派遣を行ってはいけない業務に
「その他政令で定める業務」
というものがあります。
具体的には、
・医業(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
・歯科医業(病院、診療所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
・調剤の業務(病院、診療所において行われるものに限る)
・保健師、助産師、看護師等(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅((介護予防)訪問入浴介護に係るものを除く)に限る)
・管理栄養士の業務(病院、診療所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
・歯科衛生士の業務(病院、診療所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
・放射線技師の業務(病院、診療所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
・歯科技工士の業務(病院、診療所に限る)
なお、
上記の業務でも
紹介予定派遣、産前産後休業・育児休業・介護休業代替業務、就業場所が僻地にある場合は、
労働者派遣が認められています。
【派遣法を読み解く】第4条 業務の範囲① [2020.11.10]
この条では、労働者派遣を行ってはいけない以下の業務を定めています。
①港湾運送業務
船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送や港湾倉庫への貨物搬入・搬出、荷捌きの業務等。
②建設業務
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業またはこれらの準備の作業に関する業務。
ただし、以下の業務は労働者派遣を行ってもOKとされています。
建設現場での事務業務や、施工管理業務(工事の施工計画の作成し、工程、品質安全管理等を行う業務)
③警備業務
・事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
④その他政令で定める業務
最新記事
- 賞与・手当等を支給していない協定対象派遣労働者も含めての 平均額とする必要があるのか。
- 賞与・手当等を平均額ではなく、中央値を使うことは可能か。
- 派遣労使協定の賞与算出方法
- 複数の地域に協定対象派遣労働者を派遣している場合、その複数の地域の地域指数の平均値を使うことは可能か。
- 社内の賃金テーブルと能力・経験調整指数をどのように対応させればよいか。
- 能力・経験調整指数の適用について、例えば、勤続が5年目の協定対象派遣労働者については、必ず「5年」の指数を使用する必要があるか。
- 能力・経験調整指数を勤続「0.5年(半年)」目相当に該当すると判断した場合、年数より更に細かく区切った能力・経験調整指数を使うことは可能か。
- 4年、8年、15年など、能力・経験調整指数として具体的に示されていない年数になった場合は、一般賃金の額をどのように算出すればよいか。
- 賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計に同様の職種がある場合、どちらを選択すればよいのか。
- 「基準値(0年)」の金額が地域別最低賃金の額を下回っていた場合
月別記事
- 2025年9月 ( 3 )
- 2025年8月 ( 2 )
- 2024年12月 ( 2 )
- 2024年10月 ( 2 )
- 2024年9月 ( 4 )
- 2024年8月 ( 4 )
- 2024年5月 ( 1 )
- 2024年3月 ( 1 )
- 2024年1月 ( 1 )
- 2023年12月 ( 3 )
- 2023年11月 ( 2 )
- 2023年10月 ( 2 )
- 2023年9月 ( 1 )
- 2023年8月 ( 3 )
- 2023年7月 ( 1 )
- 2023年6月 ( 2 )
- 2023年5月 ( 3 )
- 2023年4月 ( 1 )
- 2023年3月 ( 3 )
- 2023年2月 ( 4 )
- 2023年1月 ( 3 )
- 2022年8月 ( 4 )
- 2022年7月 ( 6 )
- 2022年6月 ( 5 )
- 2021年10月 ( 6 )
- 2021年9月 ( 9 )
- 2021年8月 ( 9 )
- 2021年7月 ( 9 )
- 2021年6月 ( 8 )
- 2021年5月 ( 9 )
- 2021年4月 ( 9 )
- 2021年3月 ( 12 )
- 2021年2月 ( 18 )
- 2021年1月 ( 16 )
- 2020年12月 ( 17 )
- 2020年11月 ( 5 )
- 2020年10月 ( 5 )
- 2020年3月 ( 2 )
- 2020年2月 ( 4 )
- 2020年1月 ( 3 )
- 2019年11月 ( 15 )
- 2019年10月 ( 21 )
- 2019年9月 ( 19 )
- 2019年8月 ( 21 )
- 2019年5月 ( 1 )
- 2017年12月 ( 1 )
- 2017年11月 ( 1 )
- 2017年10月 ( 1 )
- 2022.08.12
- 【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ
- 2022.08.08
- 【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?
- 2022.08.04
- 【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?
- 2022.08.01
- 【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?
- 2022.07.30
- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?
- 2023.05.12
- 派遣会社の調査について
- 2020.12.28
- 年末年始休業のお知らせ
- 2016.12.24
- 年末年始休業のお知らせ