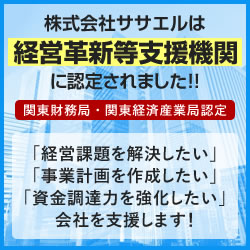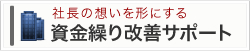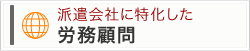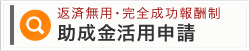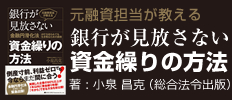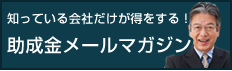- 株式会社ササエル ホーム
- 派遣ニュース
派遣労働者の同一労働同一賃金④待遇を決定する際の規定の整備 [2019.10.15]
不合理な待遇差を解消するため、【派遣先均等・均衡方式】【労使協定方式】のいずれかの方式により、派遣労働者の待遇を確保することが義務化されます。
【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇
「均等待遇」の内容:
① 職務内容(※1) 、②職務内容・配置の変更範囲が同じ場合には差別的取扱いを禁止
「均衡待遇」の内容:
① 職務内容(※1)、②職務内容・配置の変更範囲、③その他 の事情の相違を考慮して不合理な待遇差を禁止
※1職務内容とは、「業務の内容」+「責任の程度」をいいます。
★ 職務の内容等を勘案した賃金の決定 <努力義務>
派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者(無期雇用フルタイム)との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案して賃金(※2)決定するように努めなければなりません。
(※2)職務の内容に密接に関連して支払われる賃金以外の賃金(例えば、通勤手当、家族手当、住宅手当、 別居手当、子女教育手当)を除く。
【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇
過半数労働組合又は過半数代表者(過半数労働組合がない場合に限ります)と派遣元事業主との間で一定の事項を定めた労使協定を書面で締結し、労使協定で定めた事項を遵守しているときは、一部の待遇を除き(※)、この労使協定に基づき待遇が決定されることとなります。 ただし、労使協定が適切な内容で定められていない場合や労使協定で定めた事項を遵守していない場合には、【労使協定方式】は適用されず、【派遣先均等・均衡方式】が適用されます。
(※)次の①及び②の待遇については、労使協定方式による場合であっても、労使協定の対象とはならないため、派遣元事業主は、派遣先の通常の労働者との均等・均衡を確保する必要があります。
① 派遣先が、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練(法第40条第2項の教育訓練)
② 派遣先が、派遣先の労働者に対して利用の機会を与える給食施設、休憩室及び更衣室(法第40条第3項の福利厚生施設
派遣労働者の同一労働同一賃金③派遣労働者の待遇改善までの流れ [2019.10.11]
【労使協定方式】の場合(過半数代表者の選出<過半数労働組合がない場合> 投票、挙手等の民主的な方法により選出 (派遣元))
通知で示された最新の統計を確認
労使協定の締結(派遣元)(※)労使協定における賃金の定めを就 業規則等に記載
労使協定の周知等(派遣元)
1)労働者に対する周知
2)行政への報告
↓
比較対象労働者の待遇情報の提供 (派遣先) (※)教育訓練及び福利厚生施設に限る
↓
派遣料金の交渉(派遣先は派遣料金に関して配慮)
↓
労働者派遣契約の締結(派遣元及び派遣先)
↓
派遣労働者に対する説明(派遣元)
- 雇入れ時 ・ 待遇情報の明示・説明
- 派遣時 ・ 待遇情報の明示・説明 ・就業条件の明示
(注)同種の業務に従事する一般労働者の平均賃金に 変更があったときは、派遣元は、協定改定の必要性を確認し、必要に応じて、上記の流れに沿って対応します。
派遣労働者の同一労働同一賃金②派遣労働者の待遇改善までの流れ [2019.10.10]
【派遣先均等・均衡方式】の場合
比較対象労働者の待遇情報の提供(派遣先)
↓
派遣労働者の待遇の検討・決定(派遣元)
↓
派遣料金の交渉(派遣先は派遣料金に関して配慮)
↓
労働者派遣契約の締結(派遣元及び派遣先)
↓
派遣労働者に対する説明(派遣元)
- 雇入れ時 ・ 待遇情報の明示・説明
- 派遣時 ・ 待遇情報の明示・説明 ・就業条件の明示
派遣労働者に対する比較対象労働者との待遇 の相違等の説明(派遣元)
派遣労働者の同一労働同一賃金①基本的な考え方 [2019.10.09]
派遣労働者の就業場所である派遣先において、待遇に関する派遣労働者の納得感を考慮するため、
派遣先の労働者との均等(=差別的な取扱いをしないこと)、
派遣先の労働者ろの均衡(=不合理な待遇差を禁止すること)が、重要な観点となります。
しかし、派遣先が変わるごとに賃金水準が変わり、派遣労働者の所得が不安定になることが想定され、また、一般に賃金水準は大企業であるほど高く、小規模の企業であるほど低い傾向にあります。
派遣労働者が担う職務の難易度は、同種の業務であっても、大企業ほど高度で小規模の企業ほど容易とは必ずしも言えないため、結果として、派遣労働者個人の段階的・体系的なキャリアアップ支援と不整合な事態を招くこともあり得ます。
こうした状況を踏まえ、改正により、派遣労働者の待遇について、派遣元事業主には、以下のいずれかを確保することが義務化されます。
【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇
【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇
各事業主において、以下の2点を徹底することが必要となります。
① 職務の内容(業務の内容+責任の程度)や職務に必要な能力等の内容を明確化。
② ①と賃金等の待遇との関係を含めた待遇の体系全体を、派遣労働者を含む労使の話合いによって確認し、派遣労働者を含む労使で共有。
派遣先管理台帳の作成、記録、保存および記載事項の通知とは? [2019.10.08]
派遣先は、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに、次に掲げる事項を記載しなければなりません。
① 派遣労働者の氏名
② 派遣元事業主の氏名又は名称
③ 派遣元事業主の事業所の名称
④ 派遣元事業主の事業所の所在地
⑤ 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別
⑥ 派遣就業をした日
⑦ 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
⑧ 従事した業務の種類
⑨ 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位
⑩ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
⑪ 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
⑫ 教育訓練を行った日時及び内容
⑬ 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
⑭ 期間制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
⑮ 派遣元事業主から通知を受けた派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(「無」の場合は、その具体的な理由を付すこと。)
また派遣先は、派遣先管理台帳を3年間保存しなければなりません。
派遣先責任者の選任とは? [2019.10.07]
派遣先は、労働者派遣された派遣労働者に関する就業の管理を一元的に行う「派遣先責任者」を選任し、派遣労働者の適正な就業を確保しなければなりません。
派遣労働者の数について1人以上100人以下を1単位とし、1単位につき1人以上ずつ選任しなければなりません。
事業所等における派遣労働者の数と当該派遣先が雇用する労働者の数を加えた数が5人以下のときについては選任することは要しません。
派遣先は、派遣先責任者の選任に当たっては、労働関係法令に関する知識を有する者であること、人事・労務管理等について専門的な知識又は相当期間の経験を有する者であること、派遣労働者の就業に係る事項に関する一定の決定、変更を行い得る権限を有する者であること等派遣先責任者の職務を的確に遂行することができる者を選任するように努めなければなりません。
離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止とは? [2019.10.04]
派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(60 歳以上の定年退職者を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受け入れてはなりません。
派遣先は、当該労働者派遣の役務の提供を受け、上記に抵触することとなるときは、速やかに、その旨を当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に通知しなければなりません。
派遣先での常用労働者(いわゆる「正社員」)化の推進とは? [2019.10.03]
派遣先は、当該派遣先の事業所等において1年以上就業している派遣労働者について、当該事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、当該募集に係る事業所等に掲示することその他の措置を講ずることにより、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければなりません。
これは、派遣労働者の中には、いわゆる正社員での直接雇用を希望しつつも、やむを得ず派遣就労に従事している者も存在していることから、これらの者について正社員として雇用される可能性の機会をできるだけ提供しようとするものです。
派遣労働者の雇用の努力義務とは? [2019.10.02]
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について派遣元事業主から継続して1年以上派遣受入期間以内の期間労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣労働者を遅滞なく雇い入れるよう努めなければなりません。
これは、派遣先における常用雇用労働者の派遣労働者による代替の防止を確保するとともに、常用雇用を 希望する派遣労働者の常用雇用への移行を促進するためのものです。
派遣労働者個人単位の派遣可能期間制限の適切な運用とは? [2019.10.01]
派遣労働者が当該派遣先事業所において、同一の組織単位で働くことができる期間の上限は3年です。
ここでいう「組織単位」とは、「名称のいかんを問わず、業務の関連性に基づいて派遣先が設定した労働者の配置の区分であって、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分及び当該業務に係る労務管理に関して直接の権限を有する者」とされています。
なお、「派遣労働者個人単位の派遣可能期間制限」は「事業所単位の派遣可能期間制限」にある延長期間はありません。
最新記事
- 賞与・手当等を支給していない協定対象派遣労働者も含めての 平均額とする必要があるのか。
- 賞与・手当等を平均額ではなく、中央値を使うことは可能か。
- 派遣労使協定の賞与算出方法
- 複数の地域に協定対象派遣労働者を派遣している場合、その複数の地域の地域指数の平均値を使うことは可能か。
- 社内の賃金テーブルと能力・経験調整指数をどのように対応させればよいか。
- 能力・経験調整指数の適用について、例えば、勤続が5年目の協定対象派遣労働者については、必ず「5年」の指数を使用する必要があるか。
- 能力・経験調整指数を勤続「0.5年(半年)」目相当に該当すると判断した場合、年数より更に細かく区切った能力・経験調整指数を使うことは可能か。
- 4年、8年、15年など、能力・経験調整指数として具体的に示されていない年数になった場合は、一般賃金の額をどのように算出すればよいか。
- 賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計に同様の職種がある場合、どちらを選択すればよいのか。
- 「基準値(0年)」の金額が地域別最低賃金の額を下回っていた場合
月別記事
- 2025年9月 ( 3 )
- 2025年8月 ( 2 )
- 2024年12月 ( 2 )
- 2024年10月 ( 2 )
- 2024年9月 ( 4 )
- 2024年8月 ( 4 )
- 2024年5月 ( 1 )
- 2024年3月 ( 1 )
- 2024年1月 ( 1 )
- 2023年12月 ( 3 )
- 2023年11月 ( 2 )
- 2023年10月 ( 2 )
- 2023年9月 ( 1 )
- 2023年8月 ( 3 )
- 2023年7月 ( 1 )
- 2023年6月 ( 2 )
- 2023年5月 ( 3 )
- 2023年4月 ( 1 )
- 2023年3月 ( 3 )
- 2023年2月 ( 4 )
- 2023年1月 ( 3 )
- 2022年8月 ( 4 )
- 2022年7月 ( 6 )
- 2022年6月 ( 5 )
- 2021年10月 ( 6 )
- 2021年9月 ( 9 )
- 2021年8月 ( 9 )
- 2021年7月 ( 9 )
- 2021年6月 ( 8 )
- 2021年5月 ( 9 )
- 2021年4月 ( 9 )
- 2021年3月 ( 12 )
- 2021年2月 ( 18 )
- 2021年1月 ( 16 )
- 2020年12月 ( 17 )
- 2020年11月 ( 5 )
- 2020年10月 ( 5 )
- 2020年3月 ( 2 )
- 2020年2月 ( 4 )
- 2020年1月 ( 3 )
- 2019年11月 ( 15 )
- 2019年10月 ( 21 )
- 2019年9月 ( 19 )
- 2019年8月 ( 21 )
- 2019年5月 ( 1 )
- 2017年12月 ( 1 )
- 2017年11月 ( 1 )
- 2017年10月 ( 1 )
- 2022.08.12
- 【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ
- 2022.08.08
- 【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?
- 2022.08.04
- 【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?
- 2022.08.01
- 【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?
- 2022.07.30
- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?
- 2023.05.12
- 派遣会社の調査について
- 2020.12.28
- 年末年始休業のお知らせ
- 2016.12.24
- 年末年始休業のお知らせ