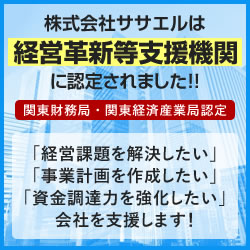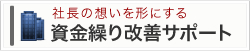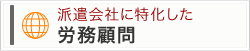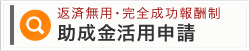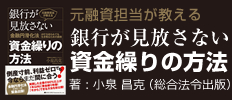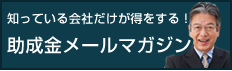- 株式会社ササエル ホーム
- 派遣ニュース
【派遣情報_第20回】派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A② [2021.07.19]
派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A
2つ目の質問を見ていきましょう。
1.契約内容等
問1-2
派遣労働者がテレワークのみにより就業を行うことは可能か。
答
派遣労働者の就業をテレワークのみにより行うことは可能であるが、以下の点などに十分に留意し実施することが必要となる。
・労働者派遣契約において、自宅等の具体的な派遣就業の場所を記載すること。
なお、派遣労働者と打合せを行う場合等に派遣先の事業所等で派遣就業を行う可能性がある場合には、必ずその旨を明記すること。
・派遣労働者が、通常の労働者派遣の取扱いと同様に、派遣元責任者及び派遣先責任者に迅速に連絡をとれるようになっていること。
・派遣労働者においても「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」に基づいた雇用管理が必要であること。
また、派遣就業の全期間の業務遂行において、派遣先からの指揮命令等のコミュニケ ーション等が円滑に行われるかを派遣先及び派遣労働者に十分に確認することが望ましいものである。
※「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html
【派遣情報_第19回】派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A① [2021.07.15]
令和2年8月 26 日公表(令和3年2月4日更新)された
派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A
について見ていきましょう。
コロナ禍によって、派遣労働者がテレワーク勤務することも増えてきました。
労働局においても、それに関する質問が増えているため、Q&Aが公表されています。
1.契約内容等
問1-1
派遣労働者がテレワークにより就業を行う場合、労働者派遣契約は、どのように記載すればよいか。
答
労働者派遣契約には、労働者派遣法第 26 条第1項第2号及び第3号に基づき、派遣先の事業所だけでなく、具体的な派遣就業の場所を記載するとともに、所属する組織単位及び指揮命令者についても明確に定めることが必要となる。
このため、労働者派遣契約には、 例えば、次のとおり記載することが考えられる。
また、個人情報保護の観点から、派遣労働者の自宅の住所まで記載する必要はないことに留意すること。
(例1:派遣先の事業所に出社する就業を基本とし、必要に応じてテレワークにより就業する場合) ・ 派遣先の事業所:○○株式会社○○営業所
就業の場所:○○株式会社○○営業所○○課○○係(〒・・・-・・・・○○県○○市○○○ Tel****-****)
ただし、必要に応じて派遣労働者の自宅
・ 組織単位:○○株式会社○○営業所○○課
・ 指揮命令者:○○株式会社○○営業所○○課○○係長○○○○
(例2:テレワークによる就業を基本とし、必要が生じた場合(週1~2日程度)に派遣先の事業所に出社して就業する場合)
・ 派遣先の事業所:○○株式会社○○営業所 就業の場所:派遣労働者の自宅
ただし、業務上の必要が生じた場合には、○○株式会社○○営業所○○課○○係での週1~2日程度の就業あり(〒・・・-・・・・○○県○○市○○○○ Tel****-****)
・ 組織単位:○○株式会社○○営業所○○課
・ 指揮命令者:○○株式会社○○営業所○○課○○係長○○○○
(例3:自宅に準じる場所(例えば、サテライトオフィスや特定の場所)で就業する場合)
・ 派遣先の事業所:○○株式会社○○支社(〒・・・-・・・・○○県○○市○○○ Tel****- ****)
就業の場所:派遣先所有の所属事業場以外の会社専用施設(専用型オフィス)又は派遣先が契約(指定)している他会社所有の共用施設(共用型オフィス)のうち、 派遣労働者が希望する場所
・ 組織単位:○○株式会社○○支社○○課
・ 指揮命令者:○○株式会社○○支社○○課○○係長○○○○
【派遣情報_第18回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑯ [2021.07.12]
労働者事業報告書の記載内容について、
今回は「様式第11号(第9面)Ⅱ6月1日現在の状況報告」
2.過去1年以内に労働者派遣されたことのある登録者(雇用されている者を含む)の数
3.雇用保険及び社会保険の派遣労働者への適用状況
について見ていきましょう。
2.過去1年以内に労働者派遣されたことのある登録者(雇用されている者を含む)の数
6月1日現在において労働者派遣事業に係る登録者であった者の実数を記載します。(同日に派遣されている労働者を含み、過去1年以内において派遣されたことがない派遣労働者を除きます。)
3.雇用保険及び社会保険の派遣労働者への適用状況
報告の対象となる6月1日現在において派遣していた派遣労働者((第7面)Ⅱ1①派遣労働者計)について、それぞれの保険の種類ごとに、適用されている者の実人数を記載します。
※6月1日現在において派遣していない者は除きます。
【派遣情報_第17回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑮ [2021.07.08]
労働者事業報告書の記載内容について、
今回は「様式第11号(第9面)Ⅱ6月1日現在の状況報告」
1.派遣労働者の実人数
⑦「日雇派遣労働者の業務別実人数(⑤の内数)」
⑧「日雇派遣労働者のうち期間制限の対象外となる業務における派遣労働者の実人数(⑤の内数)」
について見ていきましょう。
⑦「日雇派遣労働者の業務別実人数(⑤の内数)」について
⑤欄「日雇派遣労働者の実人数」のうち、労働者派遣法施行令第4条第1項第1号から第19号までに掲げる業務に従事していた日雇派遣労働者の実人数を記載します(⑤欄に記載した日雇派遣労働者計の内数となります)。
複数種類の業務に従事した日雇派遣労働者については、報告の対象となる6月1日現在においてもっとも多く従事した業務に従事したものにします。
「4-19 看護業務」については、労働者派遣法施行令第4条第2項の規定に基づき准看護師等の看護師以外の者が行う業務を含みません。
⑧「日雇派遣労働者のうち期間制限の対象外となる業務における派遣労働者の実人数(⑤の内数)」について
6月1日現在における労働者派遣法第40条の2第1項第3号から第5号までに該当する労働者派遣に係る日雇派遣労働者の実人数(1欄の③欄に記載した日雇派遣労働者計の内数)を記載します。
なお、複数の事項に該当する派遣労働者については、報告の対象となる6月1日現在においてもっとも該当する事項に記載します。
【派遣情報_第16回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑭ [2021.07.05]
労働者事業報告書の記載内容について、
今回は「様式第11号(第9面)Ⅱ6月1日現在の状況報告」
1.派遣労働者の実人数
⑤「日雇派遣労働者の実人数」
⑥「特定製造業務従事者である日雇派遣労働者の実人数(⑤ⅰ~ⅳの合計)」
について見ていきましょう。
⑤「日雇派遣労働者の実人数」について
「日雇派遣労働者」のうち、「高齢者」とは労働者派遣法施行令第4条第2項第1号に掲げる者のことをいい、「昼間学生」とは同項第2号に掲げる者のことをいい、「副業として従事する者」とは同項第3号に該当する者であって労働者派遣法施行規則第28条の3第1項第1号に該当するもののことをいい、「主たる生計者でない者」とは労働者派遣法施行令第4条第2項第3号に該当する者であって労働者派遣法施行規則第28条の3第1項第2号に該当するものをいいます。
当該日雇派遣労働者が、複数の種類に該当する場合、もっとも主たる理由と考えられるものに算定することとなります。
⑥「特定製造業務従事者である日雇派遣労働者の実人数(⑤ⅰ~ⅳの合計)」について
⑤欄「日雇派遣労働者の実人数」のうち、「特定製造業務」に従事していた日雇派遣労働者の実人数を記載します。(⑤欄に記載した日雇派遣労働者計の内数となります)
【派遣情報_第15回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑬ [2021.07.01]
労働者事業報告書の記載内容について、
今回は「様式第11号(第8面)Ⅱ6月1日現在の状況報告」
1.派遣労働者の実人数
③「特定製造業務従事者の実人数(①の内数)」
④「期間制限の対象外となる労働者派遣に係る派遣労働者(日雇派遣労働者を除く)の実人数(① の内数)」
について見ていきましょう。
③「特定製造業務従事者の実人数(①の内数)」について
労働者派遣法附則第4項の「特定製造業務」に従事した派遣労働者の実人数を記載します。
「特定製造業務」とは、物の製造業務で、育児休業等取得者の代替(産前産後休業及び育児休業、並びに産前休業に先行し、又は産後休業若しくは育児休業に後続する休業の場合における代替業務)及び、介護休業取得者の代替(介護休業及び介護休業に後続する休業であって、育児・介護休業法第2条第4号に規定する対象家族を介護するためにする休業をする場合における代替業務)以外のものをいいます。
④「期間制限の対象外となる労働者派遣に係る派遣労働者(日雇派遣労働者を除く)の実人数(① の内数)」
6月1日現在における労働者派遣法第40条の2第1項第2号から第5号までに該当する労働者派遣に係る派遣労働者(日雇派遣労働者を除く。)の実人数を記載します(①欄に記載した派遣労働者計の内数となります)。
なお、複数の事項に該当する派遣労働者については、報告の対象となる6月1日現在においてもっとも該当する事項に記載します。
労働者派遣法第40条の2第1項第2号から第5号までに該当する労働者派遣とは、以下の業務となります。
「高齢者」:労働者派遣に係る派遣労働者が60歳以上の者である場合。
「有期プロジェクト業務」:事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に完了することが予定されているもの。(終期が明確でなければならない。)
「日数限定業務」:その業務が、通常の労働者の1か月間の所定労働日数の半分以下、かつ、月10日以下しか行われない業務。
「育児休業等取得者の代替」:産前産後休業及び育児休業、並びに産前休業に先行し、又は産後休業若しくは育児休業に後続する休業の場合における代替業務。
「介護休業取得者の代替」:介護休業及び介護休業に後続する休業であって、育児・介護休業法第2条第4号に規定する対象家族を介護するためにする休業をする場合における代替業務。
【派遣情報_第14回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑫ [2021.06.28]
労働者事業報告書の記載内容について、
今回は「様式第11号(第7面)Ⅱ6月1日現在の状況報告」
1.派遣労働者の実人数
①「派遣労働者(日雇派遣労働者を除く)の実人数」
②「業務別派遣労働者(日雇派遣労働者を除く)の実人数(①の内数)」
について見ていきましょう。
令和3年6月1日現在において、派遣していた派遣労働者の実人数を記載します。
日頃は派遣労働に従事している派遣労働者であっても、6月1日に派遣されなかった労働者は除きます。
「協定対象派遣労働者」欄について
労働者派遣法第30条の4第1項の協定を締結している場合は、協定対象派遣労働者の人数を内数にて記載します。
①「派遣労働者(日雇派遣労働者を除く)の実人数」について
無期雇用派遣労働者:労働者派遣法第30条の2第1項に規定する期間を定めないで雇用される派遣労働者をいいます。
有期雇用派遣労働者:労働者派遣法第30条第1項に規定する期間を定めて雇用される派遣労働者をいいます。
「通算雇用期間が1年以上の派遣労働者」:派遣元と派遣労働者の雇用契約が6月1日現在において、通算雇用期間が1年以上である派遣労働者数をいいます。
「通算雇用期間が1年未満の派遣労働者」:通算雇用期間が1年未満の派遣労働者数をいいます。
②「業務別派遣労働者(日雇派遣労働者を除く)の実人数(①の内数)」について
①「派遣労働者(日雇派遣労働者を除く)の実人数」に記載した派遣労働者の実人数を、業務の種類別ごとに記載します。
日本標準職業分類(中分類)に基づく職種に基づき、該当する派遣労働者の区分及び従事した業務の種類別に応じた実人数を所定の欄に記載します。
複数種類の業務に従事した派遣労働者については、報告の対象となる6月1日においてもっとも多く従事した業務に従事したものとすること。
なお、「66 建設従事者(建設躯体工事従事者を除く)」、「67 電気工事従事者」等については、一部派 遣禁止業務も含まれていることに留意してください。
また、「12-1 医師」等の医療従事者については、紹介予定派遣や産前産後休業の代替等の場合にのみ限定して派遣が認められていることに留意してください。
【派遣情報_第13回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑪ [2021.06.24]
労働者事業報告書の記載内容について、
今回は「様式第11号(第6面)Ⅰ年度報告」
(9)キャリアアップ措置の実績
③「キャリアアップに資する教育訓練」
について見ていきましょう。
「1 フルタイム(1年以上雇用見込み)」、「2 短時間勤務(1年以上雇用見込み)」、「3 1年未満雇用見込み」のいずれかに該当する番号に〇印を付け、別葉にして記載すること。
報告対象期間内において労働者派遣法で求められるキャリアアップ措置の要件を満たしているものを記載してください。
その上で、事業主が独自に実施したキャリアアップ措置についても追加的に記載しても構いません。
「訓練の内容等」:訓練内容が特定できるよう具体的に記載してください。
「対象となる派遣労働者」:上段については、該当する「種別」の番号を最大2つまで記載してください。下段については、各年ごとの対象となる派遣労働者の実人数をそれぞれ記載してください。
※「対象となる派遣労働者」について、「訓練内容に係る能力を十分に有していることが明確な者」は、受講済みとして扱い、「対象となる派遣労働者数」に算入しなくても構いません。
※登録中の者は、キャリアアップに資する教育訓練の対象となる派遣労働者に含まれません。
「(上段)実施時間の総計」:各受講者に対する教育訓練実施時間の各年の1年間の合計(受講者数×教育訓練1コマの時間(複数回実施の場合は、その合計))を記載します。
対象となる派遣労働者に対して、ある訓練を1年目、2年目とそれぞれ段階ごとに行う場合は、1つの同じコースの中で、それぞれの年数の欄に記載すること。
また、同一の派遣労働者に行う訓練であっても、2年目以降は1年目とは異なるコースに位置づける訓練等の場合は、2つ以上の異なるコースとして、それぞれの年数に応じた欄に記載します。
※「訓練内容に係る能力を十分に有していることが明確な者」を受講済みとした訓練については、当該者は実際には訓練を受講していないので、「(上段)実施時間の総計」に算入することはできません。
「(下段)受講者の実人数」:各年ごとの受講者の実人数を記載します。
各年に同一の訓練を複数回受講した者は、同年内に重複計上できません(例えば、1年目と2年目に同一の訓練を複数回受講した者は、それぞれの年数の欄に1人ずつ計上することになります)。
「OJT」:業務の遂行の過程内において行う教育訓練をいいます。
「OFF-JT」:OJT以外の教育訓練のことをいいます。
※キャリアアップに資する教育訓練としてOJTを実施するに当たっては、派遣先と事前に調整等を行った上で計画的なOJTを実施しなければならなりません。
「訓練費負担の別」:
「1無償(実費負担なし)」とは、テキスト代等を含め教育訓練の全てを無償で実施することをいいます。
「2 無償(実費負担あり)」とは、テキスト代や材料費等の実費負担があるが原則として無償で実施することをいいます。
「3 有償」とは、上記以外をいいます。
「賃金支給の別」:
「1 有給(無給部分なし)」とは、用意した全ての教育訓練の実施に当たって給与を支払う場合をいいます。
「2 有給(無給部分あり)」とは、自主的に実施する教育訓練については無給とする場合があるが原則として教育訓練の実施に当たって給与を支払う場合をいいます。
「3 無給」とは、教育訓練の実施時に給与を支払わない場合をいいます。
「厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について1人当たりの平均実施時間」:
「各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の「実施時間の総計」の合計」÷「各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の受講者の実人数」で算出された数字を記載します(小数点以下切り捨て)。
※合計する各年ごとの訓練実施時間は、キャリアアップに関する要件を満たすもの(厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練)のみを合計したものとなります。
厚生労働大臣が定める基準について
①「訓練の方法の別」が「1 計画的なOJT」又は「2 OFF-JT」
②「訓練費負担の別」が「1 無償(実費負担なし)」
③「賃金支給の別」が「1 有給(無給部分なし)」である等
※フルタイム勤務の者であって1年以上の雇用見込みのあるものについては、1年で概ね8時間以上とすることとされています。
「1~3年目のaの合計(c)」及び「1~3年目のbの合計(d)」:それぞれ1年目から3年目までの値を合計した数字を記載します。
「1~3年目の厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について1人当たりの平均実施時間(c÷d)」 :上記の(c)を(d)で除して算出された数字を記載します(小数点以下切り捨て)。
4 「「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって支払った賃金額(1人1時間当たり平均)」 :キャリアアップに資する教育訓練時に支払った賃金の平均額を記載します。
【派遣情報_第12回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑩ [2021.06.21]
労働者事業報告書の記載内容について、
今回は「様式第11号(第6面)Ⅰ年度報告」
(9)キャリアアップ措置の実績
①「キャリアコンサルティングの窓口担当者の人数」
②「キャリアコンサルティングの実施状況」
について見ていきましょう。
まずは、
キャリアアップ措置とはどういうものかについて確認しておきましょう。
派遣元事業主は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、
①段階的かつ体系的な教育訓練
②希望者に対するキャリアコンサルティング
を実施する義務があります。
教育訓練計画の内容としては、
①派遣元事業主に雇用されている派遣労働者全員を対象とするものであること
②有給、無償で実施されるものであること
③派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること
④入職時の訓練が含まれたものであること
⑤無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容であること
希望者に対するキャリアコンサルティングとは、
①相談窓口には、担当者(キャリアコンサルティングの知見を有する者)が配置されていること
②希望する全ての派遣労働者がキャリアコンサルティングを受けられること
とされています。
①「キャリアコンサルティングの窓口担当者の人数」について
「キャリアコンサルタント」とは、
厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定する者が行う試験の合格者をいいます。
「上記以外の担当者」の欄には、
キャリアコンサルタント以外の「営業職」と「その他」の総数を記載します。
「営業職」とは、派遣先との連絡調整を行う営業担当者をいいます。
「その他」とは、職業能力開発推進者や3年以上の人事職務経験を有する者をいいます。
「うち派遣元責任者との兼任状況」の欄には、キャリアコンサルティングの窓口担当者の計の内数を記載してください。
「職務経験有り」 とは、過去において職務としてキャリアコンサルティングの経験がある者、職業能力開発推進者に就任したことがある者、人事部門で3年以上の経験を積んでいる者等をいいます。 「知見のある者」 とは、過去においてキャリアコンサルティング等についての職務経験はないがその知識を有する者をいいます。
②「キャリアコンサルティングの実施状況」について
「全派遣労働者数」:報告対象期間(第1面の8欄)に在籍していた派遣労働者数(退職者も含む)を記載します。
「実施を希望した者の人数」:「全派遣労働者数」のうち、キャリアコンサルティングを希望した実人数を記載します。
「実施した者の人数」:①欄の担当者が行うキャリアコンサルティングを受けた実人数を記載します。
【派遣情報_第11回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑨ [2021.06.17]
労働者事業報告書の記載内容について、
今回は「様式第11号(第5面)Ⅰ年度報告」
(8)マージン率等の情報提供の状況
について見ていきましょう。
インターネット、帳簿の備付け、その他
該当する各欄に○印をします。
複数ある場合は、複数選択してください。
マージン率等の情報提供が派遣元事業主に義務付けられています(法第23条第5項)。
情報提供の方法は、インターネットの利用、事業所への書類の備付け、その他の適切な方法により行うこととされています(則第18条の2第1項)。
なお、マージン率の情報提供に当たっては、広く関係者、とりわけ派遣労働者にインターネットの利用により必要な情報を提供することを原則としています(派遣元指針第2 16)。
情報提供すべき事項は以下の通りです。
①派遣労働者の数
②派遣先事業所数(実数)
③労働者派遣に関する料金の額の平均額(8時間あたり)
④派遣労働者の賃金の額の平均額(8時間あたり)
⑤マージン率( 計算式:(③-④)÷③×100=マージン率 )
⑥法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等
⑦派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 ⑧その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項(福利厚生など)
最新記事
- 賞与・手当等を支給していない協定対象派遣労働者も含めての 平均額とする必要があるのか。
- 賞与・手当等を平均額ではなく、中央値を使うことは可能か。
- 派遣労使協定の賞与算出方法
- 複数の地域に協定対象派遣労働者を派遣している場合、その複数の地域の地域指数の平均値を使うことは可能か。
- 社内の賃金テーブルと能力・経験調整指数をどのように対応させればよいか。
- 能力・経験調整指数の適用について、例えば、勤続が5年目の協定対象派遣労働者については、必ず「5年」の指数を使用する必要があるか。
- 能力・経験調整指数を勤続「0.5年(半年)」目相当に該当すると判断した場合、年数より更に細かく区切った能力・経験調整指数を使うことは可能か。
- 4年、8年、15年など、能力・経験調整指数として具体的に示されていない年数になった場合は、一般賃金の額をどのように算出すればよいか。
- 賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計に同様の職種がある場合、どちらを選択すればよいのか。
- 「基準値(0年)」の金額が地域別最低賃金の額を下回っていた場合
月別記事
- 2025年9月 ( 3 )
- 2025年8月 ( 2 )
- 2024年12月 ( 2 )
- 2024年10月 ( 2 )
- 2024年9月 ( 4 )
- 2024年8月 ( 4 )
- 2024年5月 ( 1 )
- 2024年3月 ( 1 )
- 2024年1月 ( 1 )
- 2023年12月 ( 3 )
- 2023年11月 ( 2 )
- 2023年10月 ( 2 )
- 2023年9月 ( 1 )
- 2023年8月 ( 3 )
- 2023年7月 ( 1 )
- 2023年6月 ( 2 )
- 2023年5月 ( 3 )
- 2023年4月 ( 1 )
- 2023年3月 ( 3 )
- 2023年2月 ( 4 )
- 2023年1月 ( 3 )
- 2022年8月 ( 4 )
- 2022年7月 ( 6 )
- 2022年6月 ( 5 )
- 2021年10月 ( 6 )
- 2021年9月 ( 9 )
- 2021年8月 ( 9 )
- 2021年7月 ( 9 )
- 2021年6月 ( 8 )
- 2021年5月 ( 9 )
- 2021年4月 ( 9 )
- 2021年3月 ( 12 )
- 2021年2月 ( 18 )
- 2021年1月 ( 16 )
- 2020年12月 ( 17 )
- 2020年11月 ( 5 )
- 2020年10月 ( 5 )
- 2020年3月 ( 2 )
- 2020年2月 ( 4 )
- 2020年1月 ( 3 )
- 2019年11月 ( 15 )
- 2019年10月 ( 21 )
- 2019年9月 ( 19 )
- 2019年8月 ( 21 )
- 2019年5月 ( 1 )
- 2017年12月 ( 1 )
- 2017年11月 ( 1 )
- 2017年10月 ( 1 )
- 2022.08.12
- 【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ
- 2022.08.08
- 【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?
- 2022.08.04
- 【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?
- 2022.08.01
- 【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?
- 2022.07.30
- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?
- 2023.05.12
- 派遣会社の調査について
- 2020.12.28
- 年末年始休業のお知らせ
- 2016.12.24
- 年末年始休業のお知らせ